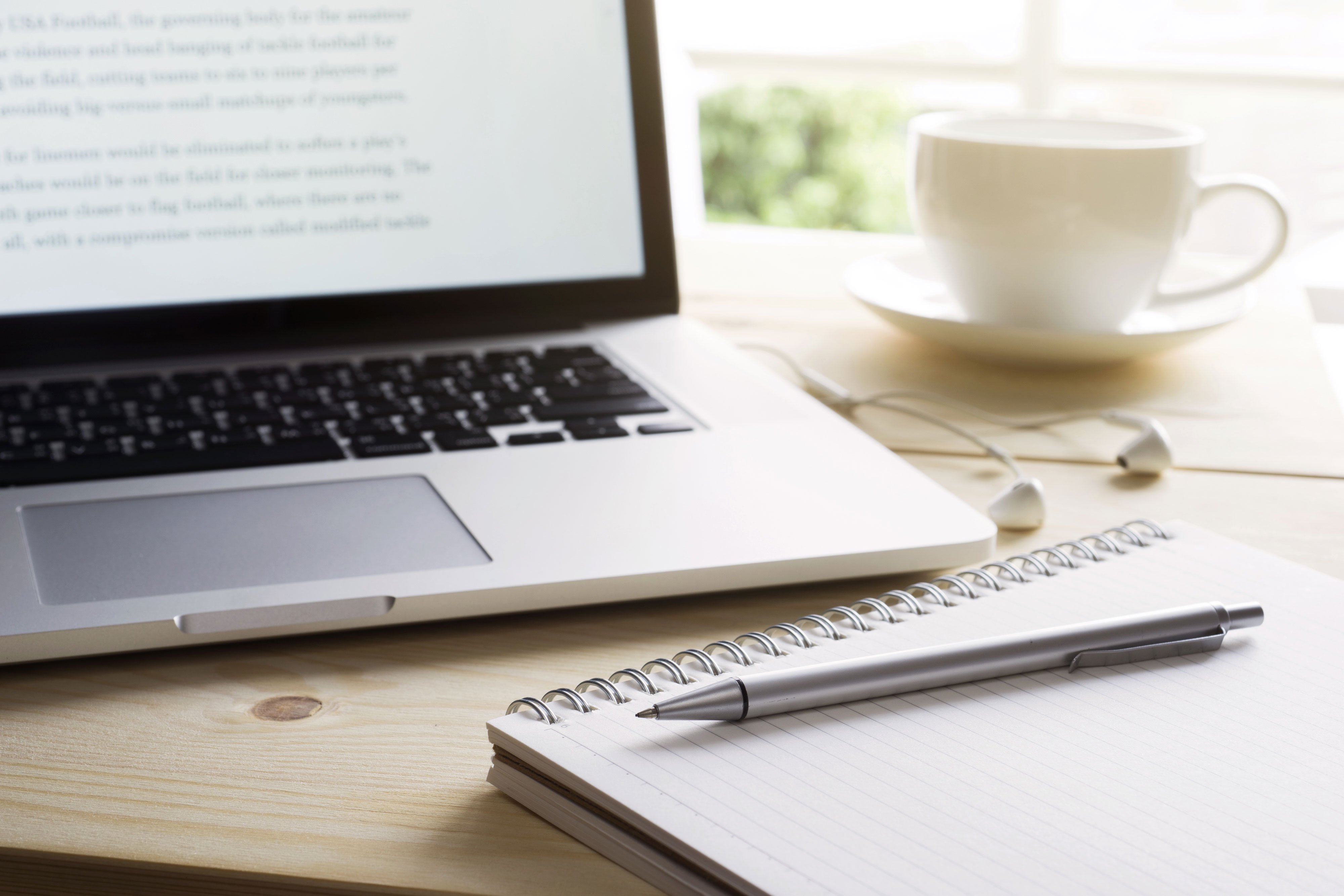【雑談】刑事弁護は黒いカラスを白いと言わせることなのか?~よくある質問シリーズ~
お世話になっております,弁護士の小見山です。
気が付けば7月になっていましたね。どうりで暑いわけです。
自宅も事務所ももうクーラーが稼働しておりますが,
先日,自宅のクーラーを稼働させたら,
けたたましい音とともに,
クーラーから何らかの物体が飛び出てきました。
触って確かめてみると,なんと氷でした。
おいおい自分じゃなくて部屋を冷ましてくれと思いましたし,
寝ぼけていたので,もしかしたら夢だったのかもしれませんが,
とりあえず稼働はしてくれているので,もはやどっちでも良いです。
これをお読みになっている方々にとっては,
もっとどっちでも良いことでしょう。
クーラーが効いた涼しい部屋でこれをお読みになっていることを祈るばかりです。
さて,いつの間にか事務局だよりが更新されていたので,
「やばい,わいも更新しなきゃ……」と思ったのはここだけの話ですが,
事務局だよりにおいて,
弁護士のイメージについてお話がありましたが,
小職自身も実際なってみるまでは,
正直同じようなふわっとしたイメージしかありませんでした。
格好良く「異議あり!!」と威勢良く法廷で立ち上がる
なんてドラマの一場面のようなことがあるんだろうなと
想像していましたが,実際にはそんな場面は滅多にありません。
尋問には主尋問と反対尋問,
裁判官からの補充尋問がありますが,
主尋問では誘導尋問しちゃあかんよーというルールになっているので,
異議を申し立てても良いのですが,
実際には,誘導尋問で引き出された供述の信用性って
必ずしも高いわけではないので,
わざわざ異議を述べなかったりします。
例えば交通事故の裁判で,
「事故当時,あなたが交差点に入った時の対面信号機の色は何色でしたか?」
というオープンな質問の場合,
証人又は本人は,「○色です。」と自ら認識した記憶を供述するのに対して,
「事故当時,あなたが交差点に入った時の対面信号機の色は青色でしたね?」
という誘導尋問の場合,答えは「はい」か「いいえ」ですから,
自分の記憶を頼りに話しているか分からず,
質問者が答えているに等しいので,
供述の証拠としての価値は低いわけです。
なので,あえて異議を述べる必要もないと考えるわけです。
現実って何だかドライですね。
何なら修習生たちの模擬裁判の方がドラマっぽいかもしれません。
あるあるシリーズでいうと,
小職が弁護士だとお話をすると,
よく「犯人を弁護するのって大変?」とか
「悪いことした人を守らなきゃいけないのって辛くないの?」
みたいな質問を頂くことがあります。
小職も刑事弁護を沢山経験してきたわけではないので,
偉そうなことを申し上げる立場にありませんし,
刑事事件の場合,そもそもの被疑事実又は公訴事実を
認めているか否かによって異なり,
認めている場合を自白事件,認めていない場合を否認事件なんて呼びますが,
小職が経験してきた刑事事件はほぼ全て自白事件です。
つまりやったことは間違いありませんと本人が認めているわけですね。
なので,「無罪を勝ち取るぜ!」的な活動をしたことはありませんし,
某MJ主演の調味料を持参するような弁護士みたいな経験はしたことがありません。
小職が経験した唯一の否認事件も起訴後の証拠をみると,
決定的な証拠(防カメとかそういうもの)があるので,
否認のしようがなく,相当説得を試みた記憶があります。懐かしい。
自白事件の場合,刑事弁護活動としては,
本人の反省を促したり,被害弁償を試みたりして,
有罪判決を前提になるべく軽い判決を求めるというのが基本になります。
「なるべく軽い判決」というと語弊がありそうですが,
「黒いカラスを白いと言わせる」的なことではなく,
「社会復帰後の環境はこんな感じで,監督者もいますよ」とか,
「被害弁償をこれだけしてますよ」といった事実を弁護側で立証し,
裁判所に情状酌量をお願いするわけです。
情状酌量という言葉を聞いたことがある方も少なくないと思いますが,
こういった犯罪事実そのものではなく,
その周辺事実なんかのことを「情状事実」なんていいますが,
これらを立証して,そういうことも考慮して判断してね,
という意味で裁判所に公平な判断を求めるわけです。
ところが,その情状でも悩むことがないわけじゃありません。
例えば,交通事故の死亡事案において,
被害者のご遺族からすれば,
加害者である被告人が免許を再取得するつもりがあるのか
ということを聞きたくなるはずですし,
免許を再取得しなければ自転車を除き交通事故の加害者になることはありませんから,
情状事実的にもそれなりに大事なとこです。
他方で,山口県の場合,正直車がないとかなり不便ですし,
場合によっては仕事的にないと無理なんて場合もあるかもしれません。
さて,皆さんが刑事弁護人だったら,
被告人は正直再取得するつもりがあると言っている場合,
法廷でどのように証言してもらいますか?
あるいは,被告人から「どう証言すれば良いでしょうか」
と聞かれたらどう答えるでしょうか。
……悩みません?
おそらくですが,
「犯人を守るの大変じゃない?」といった質問を下さるのは,
こういった場面で,取得するつもりがないと証言させるんじゃないかと
想像されている方なのではないでしょうか。
そういう先生もいらっしゃるのかもしれませんが,
小職は,被告人に再取得の意思があるのであれば,
正直に再取得するつもりがあると話さざるを得ないと思います。
確かにそのような供述をすれば,
それを聞いた被害者遺族は
「なんやこいつ反省しとるんか!!」
と憤慨するかもしれません。
ただ,小職なら,法廷で二度と免許は取りませんと言っておきながら,
後に再取得して運転しているところを見てしまった時の方が憤慨しますし,
何にも反省していなかったんだなと感じます。
また,被告人としても,
「法廷で正直に話さなかったな」というシコリのようなものが残ったり,
あるいは「何とかなったわ」的な発想でいれば,
またいずれ同じような事故を惹起しかねず,
長い目でみたら被告人のためにもならないとも思います。
何より裁判官からしても,
山口県で車を運転せずに暮らすのは難しいことは知っていますから,
再取得せずに暮らすための具体的な方策がなければ,
適当なこと言ってらぁと思われるだけかと思います。
自分が犯した罪と向き合うのは,
常に現実においてですから,
現実に再取得の必要があるのであれば,
それも素直に認めなければ真摯な反省にもならないと思うわけです。
もちろん,全ての事案がそうではなく,
事故の原因が例えば加齢による認知能力や運転能力そのものの低下にあるような場合には,
再取得自体を断念すべきだと説得すると思います。
皆さんがイメージされている弁護活動とどの程度乖離しているかは分かりませんが,
小職としては,案外被害者側に近い感覚で被疑者・被告人と接することもあるんですよー
的なことが伝わってたら幸いです。
今日も今日とてクソ暑いですし,
おそらくしばらくこの猛暑が続くんでしょうが,
皆様くれぐれも体調にはお気を付けくださいませ。
ではでは。
令和7年7月吉日
弁護士 小見山 岳