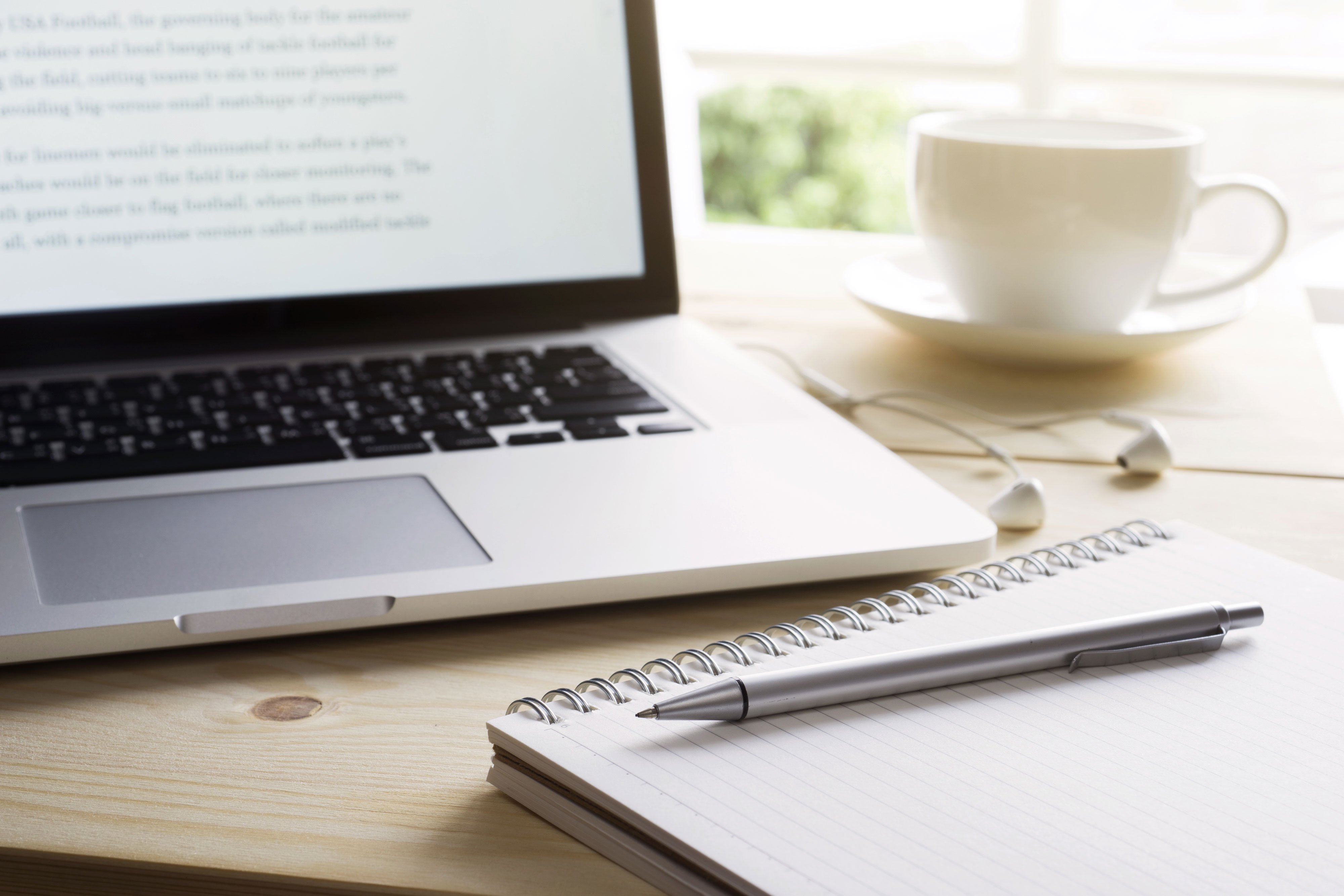【雑談】170㎝ない男に人権はないだと?~表現の自由と民法~
お世話になっております,弁護士の小見山です。
先日,かつて当事務所で勤めていらっしゃった元事務員さんが
事務所に遊びに来てくださり,
少しお話させていただいたのですが,
このお知らせを見てますよというとても嬉しい一言を頂戴しました。
よくYouTuberがコメントが励みなりますとか,
動画投稿のモチベになりますとか常套句のように言っていますが,
読んでいただいている方がいると知ると,
とんでもなくモチベーションが上がるんだなと実感しました。
もっとも,上記元事務員さんからは,
「でも最近投稿がないね笑」
と鋭い一言をも併せて頂戴してしまいました。ぐぅ。
とてもきれいな方でしたが,
美しい花には棘があるとはこのことかと思ったのはここだけの話です。
美人といえば,私事ですが,
このGWは関東に帰省させていただき,
東京はまぁ人が多くて,お祭りか?と思いましたが,
やっぱり男女ともに垢抜けている方が多いなとも思いました。
自分もイケメンだったらもっと違った人生だったのだろうか……
とあり得ない妄想にふけったことがある方は小職だけではないはず。
人の美醜をどうこう言うのは昨今あんまりよろしくないという風潮のようで,
随分前にゲーム実況者の女性YouTuberだったかが
身長170㎝ない男性は人権がないと発言して炎上したということがあったらしいです。
好きなタイプは身長170㎝以上ですと言えば大した火事にはならなかったんでしょうが,
「人権」って言葉を使ったのがきっといけなかったんでしょうね。
ちなみに小職は168㎝(小数点以下四捨五入)なので人権ないみたいです。ぐやじい。
この騒動の時もコメントやらで「人権」という言葉が飛び交っていたようですが,
小職はずっと「なんだかなぁ」と違和感を持っていました。
というのも,
皆さんは「人権」という時,その権利の主体は誰を想像するでしょうか。
「自分」,「人間」,「ありとあらゆる人」なんて答えが出てくるかなと思います。
人権は,人が人であるがゆえにそれのみで享受できる人らしく生きる権利
なんて定義されることもありますから,おそらくそんなイメージでいいんでしょう。
人権ない≒人間じゃないみたいな意味と取られてもおかしくはないので,
その意味ではやはり上記のYouTuberの発言はよろしくないですね。
身長が低くたって人間だもの。これでも牛乳飲んでるもの。
では,「人権侵害」といった時,その侵害者は誰を想像するでしょうか。
先ほどの例でいうと,実況者自身の発言が人権侵害ということになるのでしょうか。
実況者自身も人権を享有していて,
表現の自由が保障されているんだし,
不快な人は聞かなければいいだけだろうなんて反対意見もあるみたいですが,
この意見にも小職は違和感持っちゃいます。
小職と同じく違和感を持った方は,もはや以下の文章はただの駄文なので,
より有益なサイトに飛ぶことを推奨します。
違和感を持たれなかった方,又は時間のある方は,
一緒に違和感の正体を少し探ってみましょう。
さて,いきなり原始時代くらいまで遡ってみましょう笑
人類が誕生してから,
狩猟民族であれば狩りが上手な人が皆をまとめたり,
農耕民族であれば畑を耕すのが上手な人が皆をまとめたりして,
そのうち狩りの獲物を分け与えたり,
農作物を分け与えたりして,
段々と人の集団が形成されていったんだと想像しますが,
そんな時代のそんな環境でも,
多分人って争いますよね。
何かAのもらったやつの方が多くね?!とBが文句を言うとか,
あるいは,よし次の狩猟のメンバーには,
腕っぷしは弱いけど顔が良いからAにしようとリーダーが決めたら,
Aより腕っぷしの強いBは文句言うでしょう。
内容や形は違えど,学校や部活とかでたまにあるやつです。
ちなみに小職は幼少期にはおかずやお菓子を兄弟と骨肉の争いを繰り広げると,
親から,時には弟だから我慢せよと言われたり,時には兄だから我慢せよと言われ,
二男って何か不公平な気がする!と思っていました(三兄弟の真ん中の人には分かるはず)。
さて,上記の後者の例でいうと,
狩猟のメンバーの選考基準がなかなか不合理ですよね。
だって顔の美醜は狩りにあんまり影響ないっぽいですもん。
そうすると,不満を持ったBさんはどうにかしたいわけです。
Bさんが取り得る手段はいくつかあるでしょうが,
一つはリーダーに文句を言うパターンですかね。仮にパターン1としましょうか。
「先生に言いつけてやるからな」でお馴染みのやつです。
でもリーダー自体が人の美醜で狩猟メンバー決めちゃってるわけです。
リーダーもなかなか譲らないかもしれません。
何ならBより腕っぷしの強いリーダーだったら,
Bはびびって文句すら言えないかもしれません。
そうなると,もう一つ,
BさんはAさんを直接攻撃するパターンがあるかもしれません。仮にパターン2としましょう。
腕っぷしならBさんはAさんより強いですしね。
「てめえ放課後体育館裏に来いや」のパターンです。
Aさんが怪我したらさすがに次の狩猟には行けないかもしれません。
でもAさんイケメンで女子人気すごいから,
ボコボコにしたらBさん女子に嫌われちゃうかも。
ひらめいたBさんはAさんの悪口をその集団内で吹聴します。パターン3です。
もしかしたら,イケメンだけど性格はヤバいってなって,
次回の狩猟メンバーから外されちゃうなんてこともあるかもしれません。
さて,Aさん自体は何も悪いことしてないですが,
Bさんとしても,不合理な選考基準のせいでメンバーから外されてしまってやるせないわけです。
どうしたらこの集団はうまくいくのでしょうか。
そもそも事の発端は,
リーダーが意味わからん選考基準で狩猟メンバー決めたからですよね。
このリーダーが聖人君子のような方なら変なルールを作るわけがないのでしょうが,
人は往々にして間違える生き物ですから,リーダーだって間違える時くらいあります。
だったら,選考基準は皆で決めちまえばいいわけです。
皆で決めた選考基準ならBも納得まではしないけど,
まぁ仕方ないかと思えるかもしれません。
でもBさんが発言しようとしたら,
「お前に発言権はない」なんてリーダーに言われてしまったらどうでしょう。
Bさんは多分「皆で決めた」って思えないですよね。
あるいは「自分以外の皆で決めた」と思うことでしょう。
そしたらBさんは,多分パターン2か3に行くか,リーダー倒すでしょうね。
リーダーと戦う度胸なければ,多分Aさんを倒すんでしょう。
そしたらリーダーはBさん危ないからって何らか罰するかもしれませんね。
いずれにしてもこの集団がうまくいく気配がありません。
とりあえずここで言えることは,「皆で決めた」といえるためには,
リーダーに対して,その集団に所属する誰もが,
特に資格とかもいらずに,言いたいことを言える環境がないといけないわけですね。
ん?ってことは「その集団にいる人」ってだけで認められなきゃいけないのが発言権?
人が人であるというだけで認められる権利ってこと?
なんかどっかで似たようなこと聞いた気がすると感じた方もいれば,
おいおい「人権」の話しているのにどんな原始時代の話だよと思う方もいらっしゃるかもしれません。
でもこれって人間社会ではよくあることだと思います。
こと集団が成熟していない場合には多発する事象なのではないかなと。
学校や部活動などで,全く同じではないにしても,
同じような事象を見たり,あるいは経験された方もいるのではないでしょうか。
現代社会だって結局は人の集まりですから,
現代だって基本的な構造は同じはずです。
ただ人が増えれば増えるほど構成要素が複雑になるだけです。
上記の例でいうと,乱暴ですが「リーダー」を国家,
AさんやBさんはもちろん,そこに所属する人たちを「国民」と置き換えてみてください。
上記の「選考基準」が「法律」とか行政の処分って考えてみると,
何か日本でもよくあることのような気がしてきませんか。
勘の鋭い方はもうお気づきだと思いますが,
上記でいうリーダーに対する「発言権」こそが「表現の自由」ってことになります。
置き換えると,発言権,すなわち表現の自由ってリーダー,すなわち国家に対する権利なのです。
よく「表現の自由は民主主義の根幹をなす」なんて言われますが,
これはリーダーに何も言えなかったら「皆で決めた」って言えないってことなんですね。
だからリーダーは「お前に発言権はない」なんてこと言えないわけです。
ルールとしては「国は国民の発言を邪魔してはいけん」という定め方もあり得ますが,
国に対して「国民は表現の自由を有する」と定めても基本的には同じです。
いずれにしても,発言権というルールは,
その集団の人々,国民からリーダー,国家側に向けたルールなわけです。
選考基準はあくまでリーダーからその集団に向けられたルールだったのと対象的ですね。
前にジャイアンを題材に所有権のお話をした際,
国民から国家に向けられたルールを「憲法」,
国家から国民に向けられたルールを「法律」って言ったかと思いますが,
それと同じことです。
ここでいう「表現の自由」ってあくまで国民→国家の方向なので,
国民→国民って話になると,何か違和感があるわけです。
あくまでリーダーに文句言う,あるいはリーダーから邪魔されないってものなわけです。
では,リーダーではないAさんや女子が選考基準を決める会議で,
「Bは黙ってろ」って言うことはどうなんでしょうか。
あるいはその中の女子1名が「Aよりかっこ悪いBに発言権はない」といったら?
リーダーはBに黙ってろなんて言っていませんから,
発言権はBにあるわけです。
色々な事情でBが発言を控えることはあるかもしれませんが,
Bは言い返そうと思えば言い返してもいいわけです。
この「言い返してもいい」ってところからすると,
Bの発言権は保障されているわけです。
では,当該女子が「Bの顔は気持ち悪いからそういう人は選ばないで欲しい」
と言ったらどうでしょう?
当該女子だって発言権はあるわけですが,
他人を傷つけるようなことまで言っていいよって話だったら,
もう悪口大会の始まりです。ひえーまじ怖い。
ただ,これらはあくまで集団内部同士,つまり国民同士のもめごとなわけです。
国民同士のもめごとに適用すべきは,
国民同士の基本的なルールです。
あれ?国民同士の基本的なルールってなんでしたっけ?
言い換えれば「私法の一般法」はなんだったでしょう?
そう,皆さんご存じお馴染みの民法です。
例えば,民法では不法行為に基づく損害賠償請求権なんてものを定めているので,
もし当該女子が何かしらの発言で人を傷つけるようなことがあれば,
傷ついた人は民法に基づいて損害賠償なりをしていこうということになるわけですね。
そこでは,法律上保護された利益の侵害があったかどうかが問題なのであって,
別に表現の自由がどうとかって話にはならないわけです。
以上のとおりですので,「表現の自由」という権利を,
当たり前のように国民同士の関係で使われてると,
小職としては「ん?」と何か違和感を持ってしまうわけです。
ただし,「人権」という言葉自体は,極めて多義的で,
必ずしも対国家の権利というわけではないので注意が必要です。
対国家の権利と小職が言っているのは,「憲法上の権利」です。
人権って別に国がなくても享受すべきものですが,
憲法上の権利は,憲法ありき,国家ありきなのです。
乱暴なイメージですが,
源泉を「人権」,源泉を引いている宿が国家,
そこにある桧風呂が憲法で,
桧風呂にあるお湯が「憲法上の権利」って感じでしょうか。
源泉そのものには別に桧風呂がなくても入れますが,
桧風呂には宿に行かなきゃ入れない的な感じです。
また,そもそも対国家と国民同士の垣根が曖昧な権利もあります。
例えば,プライバシー権。
プライバシーって私的な領域を守るものなので,
国家が侵害することもあれば,
他人が侵害することもあるので,
憲法上の権利でもあり,
また民法上の法益でもあるわけです。
その他にも,憲法上の権利であっても,
すごーく特殊な場合には,
私人間(「しにんげん」ではなく「しじんかん」と読みます。)にも効力がある
と考えた方が良いのでは?いう考え方もあります。
上記の原始時代的な事例を乱暴に「国家」と「国民」に置き換えてみましたが,
更に乱暴に「会社」と「就活生」に置き換えてみたらどうでしょう?
会社がいわゆる顔採用していたことが発覚したり,
試用期間中に身長170㎝ないからやっぱ不採用なんてことがあれば,
就活生としてはたまったもんではありません。
会社に対して不平等だ!なんて文句を言えないというのも,
何だか違和感がありますよね。
こんな時に憲法14条に書いてある「法の下の平等」ってやつに反しているやないか!
と言いたくなる気持ちもよく分かります。
でもやっぱり平等に扱わなければならないよという「法の下の平等」は,
あくまで憲法上の権利の問題であって,
原則的に対国家との関係で問題にすべきです。
だってその会社も一企業にすぎない会社は私(法)人なので,
誰を雇うかというのは,その会社の自由であって,
国からどうこう言われる筋合いは本来ないはずだからです。
例えば,特定の宗教や思想を嫌っている企業がいて,
その特定の宗教や思想を有している人を雇わなきゃいけないと国が強制するなら,
むしろその企業の思想良心の自由や宗教の自由が侵害されてしまう
とも考えられるのです。
だからやっぱり対国家と私人間の問題は分けて考える方がいいわけです。
となると私人間に適用されるべきはやっぱり民法です。
じゃあ民法に法の下の平等という価値観がないのかというとそうではありません。
民法には公序良俗に反することはしちゃいけませんわよと
きちんと憲法の価値を反映させることができる条項があるわけです。
だったら,これ使えばええやん?わざわざ憲法持ち出さずとも,
あくまで民法のレベルで解決できるやんってなるわけです。
多様化した現代社会では,
憲法上の権利だろうが対国家的権利という図式に固執すべきではない
という考え方もあり得るとは思いますし,
実際に人を死に至らしめたり,不幸にするのは,
何も国家権力だけじゃなくて,
ネット社会におけるバッシングや,
その他諸々国民同士の関係で生じることの方がもはや多いかもしれません。
あるいは,芸能人やYouTuberは与える社会的影響が大きいから,
ある意味公人なんだって意見もあるかもしれません。
ただ,本来的に憲法上の権利は,
国家というでっかい権力持った怖いものに対抗する手段
という認識は忘れずに持っておいた方が良い気がします。
憲法上の権利を私人間に適用するというのは,
イメージ的には何かすごい強い権利を私人間でも使えるなら使おうって
考え方に近いと思いますが,
でもそれしちゃうと,憲法上の権利自体が何か法律レベルの話にならない?
という危惧があるわけです。
なんで危惧かと言えば,法律ってリーダーが決めるルールだからです。
せっかくリーダーを縛り付けるルールなのに,
何だかいつの間にか法律で憲法上の権利をどうにかできたら,
リーダー野放しにならない?大丈夫?という感覚です。
大丈夫かもしれませんが,
大丈夫じゃなかったらおおごとなので,
やっぱり慎重に考えた方がよくね?と。
だからなのかは分かりかねますが,
表現の自由とか人権って言葉を聞くと
どうしても対国家の問題という感覚があるので,
私人間でそういう話を無自覚にしているのを聞くと
どうしても違和感を持ってしまうんだと思います。
国家ってあまりにデカすぎて想像しにくいですし,
全くもって身の回りのこととして実感が湧かないと思いますが,
部活の顧問とか,会社の社長とか,
特定の集団の意思決定する人ってイメージすると,
案外想像しやすいのでは?と思ってこんな話をしてみた次第ですが,
いかがでしたでしょうか。
色々言いましたが,
小職自身あんまり政治に興味ないですし,
国がどうとか深く考えているわけではありません。
ただ,何となく法学っておもろいかもって思ってもらえたらこれ幸いです。
もっとも,本投稿は正確性を度外視していますので,
きちんとお勉強したい方はぜひ憲法の入門書とか読んでみてください。
多分秒で眠くなると思いますけど,案外おもろいですよ。
春かなと思ったら何か肌寒かったりよく分からない日もありますが,
皆様くれぐれもご体調にはお気を付けて。ではでは。
令和7年5月吉日
弁護士 小見山 岳